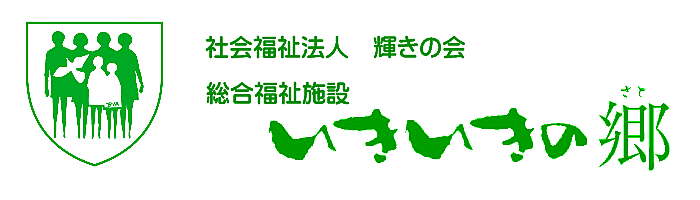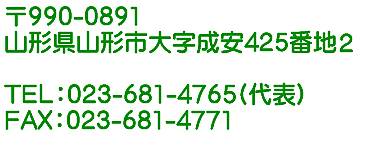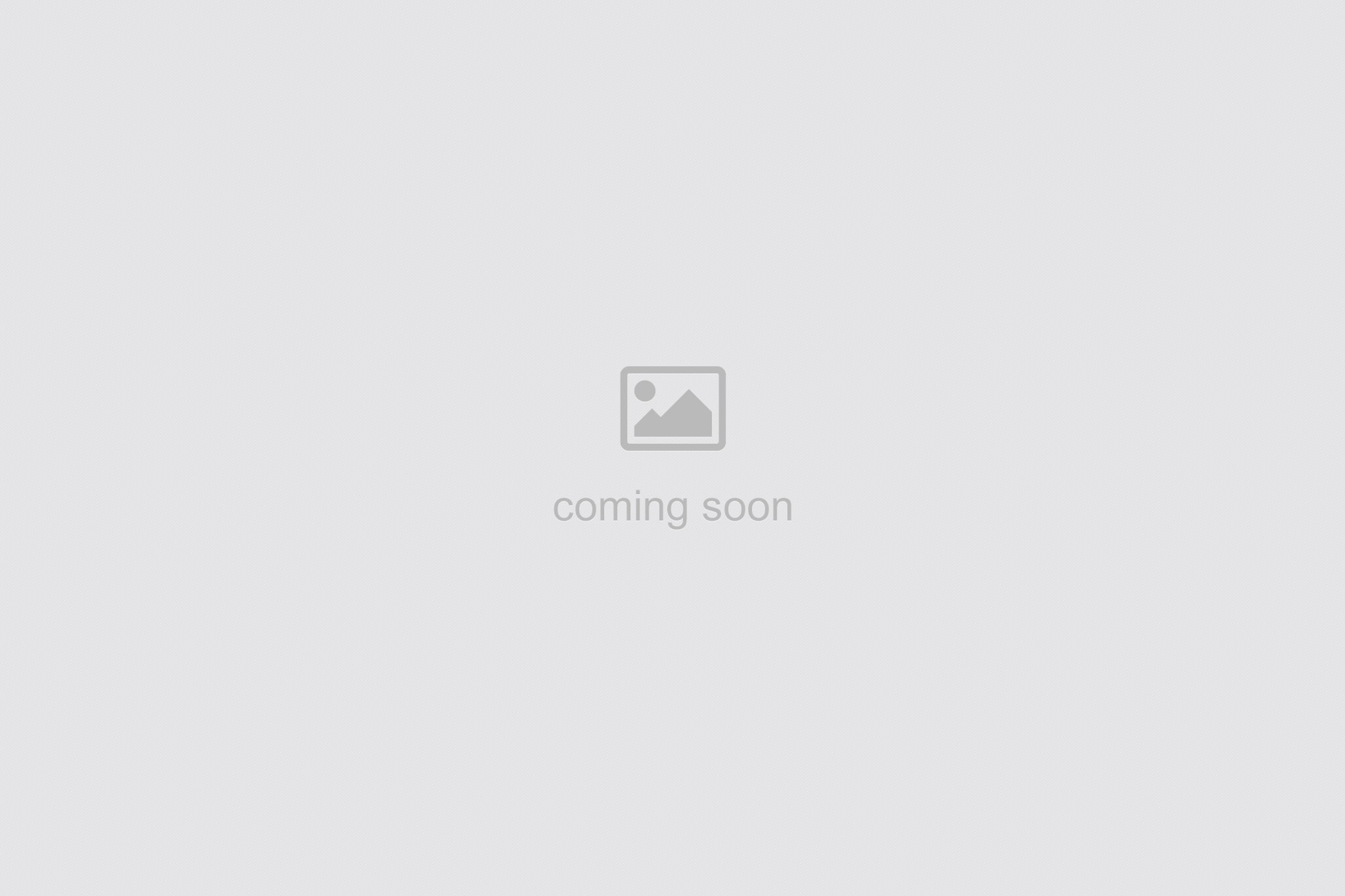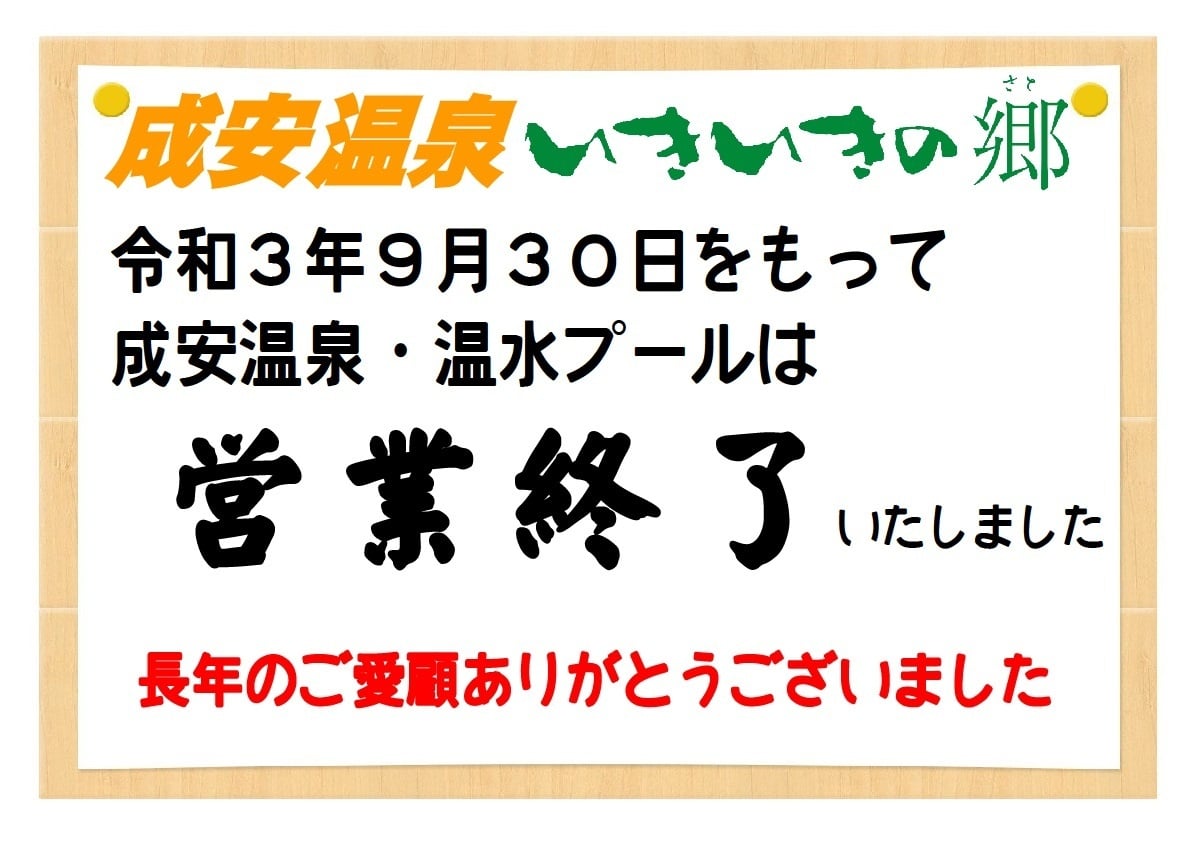新年度のご挨拶(令和7年度全体運営方針)
令和9年度に30周年を迎える。企業30年といい、創業して成長期を迎え成熟期を経てやがて衰退する、その期間だという。
高齢福祉と障害福祉を高層の建屋に収め、温泉とプールや体育館を併設運営するいきいきの郷は、大規模な、他に類を見ない地域交流型総合福祉施設として、行政の絶大なバックアップを受け、誕生した。
いきいきの郷を福祉の実践場所として選択したのは、この新奇さと規模がもたらす夢と希望だったのだろうか。
順風満帆と思われた輝きの会も、介護保険の制度の変遷にあって、特別養護老人ホーム入所基準が要介護度3以上とされた第6期計画の最終年となる平成29年度に経常増減差額が赤字になって以来現在まで、この指標が黒字になることはなかった。収入と支出のバランスが崩れ、立て直せないでいる。
新しい福祉事業に挑戦することもなく、借金も無いにも関わらず、経常増減差額が悪化する理由は何か。それは、施設の規模に対し収入が少なく、事業の規模に対し支出が多いためといわざるを得ない。
大規模な施設は、相応の減価償却費を求める。減価償却費は、積立を前提に支出に計上される。概ね6千万円であるが、これが確保できれば、経年劣化に伴い毎年費やされる修繕改善も貯金を取り崩さずに実施できる。しかし、経常増減差額はマイナスであり、減価償却費は確保されていない。
人が人を支援する福祉は労働集約型であり、高人件費率にならざるを得ない。しかし、給与規程通りに算出された令和7年度の人件費率は69.6%(令和4年社会福祉法人全国平均67.3%)である。公務員準拠の給与制度。そこに上乗せされた処遇改善制度。職員数の割に活性化しない新陳代謝。どのような理由であれ、契約した労賃は借金をしてでも支払わなければならない。借金をすれば返済金を捻出しなければならない。人件費以外の3割の支出からどのように捻出できるのか。それがいかに理路に合わないことか明白である。
解決策は、収入を得ること。いかに利用者から選ばれるかに尽きる。
職員には利用者みなさまの福祉業務に専念して欲しい。しかし、もはや、法人の業績について職員の理解と協力なくして、収支バランスを図ることが困難な状況にある。
令和5年度の決算を一般職員に説明したことを手始めに、施設長会や経営会議の報告を通して、法人の業績について共有化を図っている。厳しい状況に不安を持ち、不満として自己申告する職員もある。新年早々に30代、40代の職員の退職希望が相次いだが、事実が不安や不満を喚起したのかもしれない。職員に理解を求める難しさを思い知るが、現在、理事の半数は輝きの会の専従役員と職員である。
輝きの会に勤務する者が自ら経営の健全さに責任を負う段階に至っている。
健全な経営には人づくりが欠かせない。職員一人ひとりが法人の経営を担う経営意識と、良い福祉を勧める営業意識、その涵養を図る。現場経験者による本部勤務を進め、職員のキャリアパスを明確にし、職員による経営参画の道筋を明らかにする。
健全な経営には収支のバランスが欠かせない。人件費の管理は待ったなしだ。勤務状況や成果に基づくドラスティックな給与の決定方法を管理職から取り入れる。働き方改革に基づき勤務のあり方を点検する。仕事と個人生活の両立を法制度を超えて支援するとともに、処遇によって一般勤務との均衡を図る。24時間365日、利用者の安全と安心を守る職務にあって、自己都合による希望休やシフト変更、さらに非計画的な年休は、利用者や同僚に多大な負担を及ぼすものであり、実態を点検し、許容の範囲の程度を評価する。
健全な経営に適切な投資は欠かせない。老朽化し薄汚れた施設設備は利用者に誤解を与えかねない。終の棲家として心豊かに暮らせる施設を目指すため、施設全体をスキャン(点検)し、単なる改修ではなく、さらに良くするリノベーションを計画する。労働力不足を補う生産性向上を果たすDX化等にこれまで以上に積極的に取り組む。
健全な経営の源泉は初心にある。事業拡大や変化、挑戦を恐れては進むことができない。地域交流型総合福祉施設の再生を目指す。令和9年度を目途に、地域福祉センターを改修し、障害福祉事業とプール等の施設開放事業を行う。社会福祉施設整備補助金獲得により温泉部分を改修し(多目的スペースを構想)、障害就労支援事業を展開する。またプールを再開し(採暖室としてサウナも構想)、体育館も併せて、健康施設として地域に開放する。
輝きの会いきいきの郷に夢と希望を抱いた職員一人一人が自らの手で新しい夢と希望を作り上げること。それが令和7年度の全体方針である。
理事長 鞠子克己